片 麻痺 靴
- Rolf Reeves
- Oct 30, 2023
- 21 min read
介護用靴 (リハビリシューズ)の種類や特徴、選び方とは?おすすめ商品も紹介
加齢によって身体機能が低下すると、筋力の衰えや関節のゆがみが原因の膝の痛みなどの影響で、 若い頃のようにスムーズに歩くことが難しくなり ます。また、足首が硬くなってつまずきやすく、膝の痛みをかばうように歩いているうちに不自然な歩き方になるなど、歩行に負担を感じることが増えます。介護用靴は、そのような変化にも対応できる機能が充実していますので、 少しでも負担を軽くして快適に歩けるようサポート してくれます。

【介護用靴の目的2】足のトラブル防止のため
介護用靴は、足に合わない靴を履き続けることによる足のトラブル防止にもなります。十分な筋力がある若い間は、デザインで靴を選んでも履きこなすことができますが、足に合わない靴を長期間履き続けることで、外反母趾や、捻挫、骨折などのケガにつながる恐れがあります。高齢になってからのケガは治りにくく、ケガによる運動制限でさらに筋力が低下してしまうことも考えられます。このような足のトラブルを防ぐために、しっかり 足にフィットして安全に歩ける介護用靴を選ぶ ことが大切です。
【介護用靴の目的3】麻痺やむくみ、装具着用時にも使用可能
介護用靴は、 半身麻痺やむくみが出やすい人、装具を着用している方でも使用可能 です。介護用靴は軽くて柔らかい素材の使用、履き口が大きく作られている、マジックテープやファスナーで簡単に固定できるなど、靴が履きにくい人でも楽に履くことができるようにさまざまな工夫がされています。むくみのある人や装具を着けている人でも履きやすいように靴の幅が広いタイプもあります。
【介護用靴の目的4】自力で歩くために安全に履ける介護用靴が必要
加齢による筋力低下などで歩いて出かけることが億劫、病気やケガなどで歩く機会が少ないなど、運動量が減り筋力が低下して歩行が難しくなるというケースがたくさんあります。 自力で歩くことは、健康維持 にもつながります。できるだけ自力で歩き続けられるためにも安全に履ける介護用靴を履き日頃から意識して歩くことが大切です。足のむくみがひどい、病気や外反母趾などで足が痛むというような状態でも、履きやすくて快適に歩ける介護用靴であれば歩くことへの負担も少しは軽減できます。自力で歩こうという前向きな気持ちを持つために 滑りにくい、軽い、歩きやすいなど、安全に履くことができる介護用靴を使用 しましょう。
【介護用靴の目的5】リハビリする時にも必要なため
病院内などでのリハビリのときは、 脱ぎ履きがしやすく、歩きやすいリハビリシューズが必要 です。介護用靴とリハビリシューズに明確な違いはなく、介護用靴の中でもリハビリの際に使う安全で動きやすい靴のことをリハビリシューズと呼んでいます。リハビリシューズには、リハビリを必要としている方が簡単に履くことができ、安全に歩けるようにサポートする機能が備わっています。
介護用靴の特徴
【介護用靴の特徴1】脱ぎ履きがしやすく、足を固定できる

脱ぎ履きなどがしやすく、足が固定できるのが特徴 です。 高齢になると、腰を曲げるのがつらい、視力の低下で足先が見えにくい、手先の動きが鈍くなって思うように動かせないという方でも、脱ぎ履きがしやすいように、履き口が広く自由に曲げやすい柔らかな素材でできています。かかと部分に輪が付いていて、引っ張るだけで簡単に履けるタイプもあります。足の固定は、ヒモではなくマジックテープで調整するタイプが多いです。 着脱が楽なのはもちろんですが、足の形状に合わせて簡単に固定 することができます。靴がゆるすぎると、靴の中で足が滑って転倒につながる恐れがあるため、マジックテープで簡単に固定できるのは、安全に歩くためにも安心な機能です。
【介護用靴の特徴2】左右で足のサイズが違う、片足だけでも購入できる
介護用靴は、 左右で違うサイズの注文や、片足だけでの購入 もできます。左右の足のサイズが違うと自覚している方や、病気などで片足だけむくむことが多い方、装具を着用した状態で靴を履く必要がある人など、 左右同じサイズの靴を履くことが難しい場合にとても便利 です。
介護用靴の種類
(1)リハビリシューズ
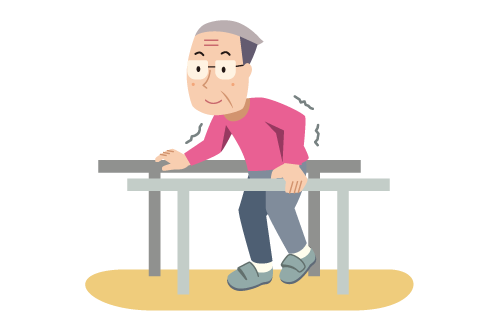
リハビリシューズは介護用靴と明確な違いはありません。ケガや病気などでリハビリが必要になったときに履く靴をリハビリシューズと呼びます。一般的な靴に比べて脱ぎ履きがしやすく、 伸縮性もあるので圧迫感を感じずに快適 に履くことができます。
(2)介護用靴
介護用靴には、高齢者が簡単に履け、 少しでも安全に歩くことができるように工夫されたデザインや機能 が備わっています。高齢になると足首の柔軟性が衰え、歩いているときにつま先が上がりにくくなるためつまずきやすくなります。このような 歩行中のつまずきを防止 するために、介護靴はつま先が少し上がっているデザインが多いです。つま先だけでなく、かかと部分が少し上がったデザインもあり、歩くときのけり出しや着地がしやすいような構造で、転倒防止にもつながるようになっています。
(3)介護用靴(半身麻痺や装具着用している方用)
半身麻痺の方、装具を着用している方用の介護用靴は、 足の甲の部分が開く、マジックテープなどで足の甲の高さに合わせて調節ができる など、 靴を履くときの負担が少しでも軽く なるように、さまざまな工夫がされています 。外反母趾やむくみによる圧迫感も考慮もされ、足先部分にゆとりがあるものや、伸縮性の高い素材が使用されているものが多いです。
介護用靴の選び方
①身体や症状に合う靴を選ぶ

介護用靴を履く人の身体状況に合ったものを選びましょう。 むくみや腫れがひどいときは、足幅のサイズ調整が簡単なマジックテープで固定できるタイプ がよいでしょう。リウマチや外反母趾などで 足先に痛みがある場合は、足先が柔らかい素材のものを選ぶ ことで、靴を履いて歩くときの痛みの軽減になります。足先に循環障害がある場合は、足先の感覚がわかりにくいことが多く、気づかないうちに足先を強く打っているケースも少なくありません。ケガ防止のためにも、足先がしっかりと覆われているタイプの靴を選びましょう。
②室内用と屋外用の靴の違いで選ぶ
介護用靴には、室内用と屋外用があります。室内用の多くは、素材が柔らかくて軽いものです。靴底に滑りにくい加工がされ、スリッパやソックス1枚で歩くよりも安心で、転倒防止にもつながります。屋外用は、撥水加工がされているタイプが多く、雨の日の外出も安心です。 室内用と屋外用では素材や構造が異なる ため、どこで履く予定なのかを考えて選びましょう。
③介護用靴のサイズだけでなく幅や高さにも注意
介護用靴を選ぶときは、足のサイズだけでなく、 幅や甲の高さなどが足に合っているかどうかも重要 です。 足のサイズでいえば、つま先に1cm程度ゆとりがあるものを選ぶとよいでしょう。足の幅は、親指と小指が靴に圧迫されることなく、側面にそっと触れる程度が最適です。足先にゆとりがないと、窮屈に感じ痛みが出るなどの恐れがあるため、中で足の指が広がるくらいを目安にして選びましょう。 足の変形やむくみがある方、装具を着用している方には、幅が広めのタイプがおすすめです。マジックテープで固定するタイプであれば、幅や甲の高さも調整しやすいので便利です。インソールが取り外せるものもあり、装具を着用している側のインソールを取り外し、身体のバランスをとりやすい高さに調整するという方法もあります。 サイズが合っていないと、指を痛める、靴の中で足が滑り転倒のリスク になります。しっかりと足に合った履き心地のよいものを選びましょう。 【靴のサイズの測り方】 足の大きさは、その日の身体状況や時間帯などによって変わることがあります。むくみが出やすい場合は、最もむくんでいる時間帯に足のサイズを測ってみることをおすすめします。また、多くの人が左右で異なる数値が出るため、必ず両足を測りましょう。
④ 装具使用の場合は、開口部が広い介護用靴を選ぶ
装具を着用していると、装具の大きさで靴が履きにくいことがあります。靴の甲部分が大きく開くタイプなど、 開口部が広い介護用靴を選びましょう 。 安全に歩くために、足を靴に入れたら、マジックテープなどでしっかり固定して足にフィットさせるようにしましょう。
⑤インターネットで買う場合も、一度試し履きしてからの購入がおすすめ
インターネットでも、介護用靴の購入ができます。ご自身のサイズが明確に分かっている、同じ物をリピートして購入するときなどにはとても便利です。しかし、介護用靴は、高齢になるにつれて感じやすい歩行に対しての不安解消や、病気やケガなどによる歩行時の身体への負担軽減をサポートすることを目的とした靴のため、はじめてご購入されるときなどは、 試し履きをしてからの購入をおすすめ します。フランスベッドが運営する介護ショップ 「リハテックショップ」では介護用靴の試し履きをすることができます
介護する側に適した靴

【1.デイサービスなどの職場で履く場合】
デイサービスなど靴を履く、脱ぐが多い職場では、紐のない靴がよいでしょう。紐があると履くのに時間がかかるため、送迎や靴の着脱介助などを行うときにすぐに適切な介助ができません。 さっと脱ぎ履きができる紐なしの靴を選びましょう 。
【2.介護施設などの職場で履く場合】
移乗介助などの身体介護が多い現場では、 フ ィット感があって足を保護できるジッパータイプの靴がよい でしょう。車椅子やベッドへの移乗などを安全に行うために、介護者の足を保護しながらしっかり踏ん張れる靴を選びましょう。 サンダルや紐靴は、ケガや転倒のリスクがある ため避けましょう。
【3.訪問介護で履く場合】
訪問介護では、訪問先で靴下に汚れが付いてしまうことあります。次の訪問先にそのまま行くことのないように、あらかじめ了承を得てビニールのスリッパなどを履くようにしましょう 。 ビニールのスリッパであれば、汚れが付いても簡単に拭き取り、水洗いも可能 ですのでおすすめです。
【4.介護を行うすべての人向け】
介護を行うときは、介護する方、される方、両方の安全を考える必要があります。介護する方は、足先が出ている靴、高いヒールの靴など機能性に優れていない靴を履いていると、介護中のケガや事故にもつながります。 安全に介護を行えるように足先がしっかりカバーされ、フィット感のある動きやすい靴 を選びましょう。介護する側の靴として、通気性がよく蒸れにくい靴、かかと部分が低い靴など、介護する上で必要な機能が備わった靴がたくさんあります。フランスベッドのECショップ「ホームケア全科オンライン」でも購入することができますので探してみてはいかがでしょうか。 ▶ 介護する方用の靴はこちら
まとめ
介護用靴は、 高齢になるにつれて感じやすい歩行に対しての不安解消や、病気やケガなどによる歩行時の身体への負担軽減をサポート します。 加齢や急な病気・ケガによってこれまでのように軽快に歩くことが難しくなった方でも、自分の足に合った履きやすい靴があれば、大きな負担を感じずに安心して歩くことができます。最近は、おしゃれなデザインの介護用靴もあります。靴を選ぶ楽しみや、お気に入りの靴が見つかれば、介護用靴を履いておでかけするという喜びにもつながります。介護用靴は、介護する側の方にとっても、介護の負担軽減や安全を守る大切なものです。 フランスベッドのリハテックショップでは試し履きできる ので、自分にあった介護用靴を選ぶことができます。もちろんフランスベッドのECショップ「ホームケア全科オンライン」でも、介護用靴を取り扱っています。たくさんある種類の中から、足に合う快適な介護用靴を見つけてみましょう。 ▶ 高齢者のための介護用靴の一覧はこちら
介護用靴 (リハビリシューズ)の種類や特徴、選び方とは?おすすめ商品も紹介
加齢によって身体機能が低下すると、筋力の衰えや関節のゆがみが原因の膝の痛みなどの影響で、 若い頃のようにスムーズに歩くことが難しくなり ます。また、足首が硬くなってつまずきやすく、膝の痛みをかばうように歩いているうちに不自然な歩き方になるなど、歩行に負担を感じることが増えます。介護用靴は、そのような変化にも対応できる機能が充実していますので、 少しでも負担を軽くして快適に歩けるようサポート してくれます。
【介護用靴の目的2】足のトラブル防止のため
介護用靴は、足に合わない靴を履き続けることによる足のトラブル防止にもなります。十分な筋力がある若い間は、デザインで靴を選んでも履きこなすことができますが、足に合わない靴を長期間履き続けることで、外反母趾や、捻挫、骨折などのケガにつながる恐れがあります。高齢になってからのケガは治りにくく、ケガによる運動制限でさらに筋力が低下してしまうことも考えられます。このような足のトラブルを防ぐために、しっかり 足にフィットして安全に歩ける介護用靴を選ぶ ことが大切です。
【介護用靴の目的3】麻痺やむくみ、装具着用時にも使用可能
介護用靴は、 半身麻痺やむくみが出やすい人、装具を着用している方でも使用可能 です。介護用靴は軽くて柔らかい素材の使用、履き口が大きく作られている、マジックテープやファスナーで簡単に固定できるなど、靴が履きにくい人でも楽に履くことができるようにさまざまな工夫がされています。むくみのある人や装具を着けている人でも履きやすいように靴の幅が広いタイプもあります。
【介護用靴の目的4】自力で歩くために安全に履ける介護用靴が必要
加齢による筋力低下などで歩いて出かけることが億劫、病気やケガなどで歩く機会が少ないなど、運動量が減り筋力が低下して歩行が難しくなるというケースがたくさんあります。 自力で歩くことは、健康維持 にもつながります。できるだけ自力で歩き続けられるためにも安全に履ける介護用靴を履き日頃から意識して歩くことが大切です。足のむくみがひどい、病気や外反母趾などで足が痛むというような状態でも、履きやすくて快適に歩ける介護用靴であれば歩くことへの負担も少しは軽減できます。自力で歩こうという前向きな気持ちを持つために 滑りにくい、軽い、歩きやすいなど、安全に履くことができる介護用靴を使用 しましょう。
【介護用靴の目的5】リハビリする時にも必要なため
病院内などでのリハビリのときは、 脱ぎ履きがしやすく、歩きやすいリハビリシューズが必要 です。介護用靴とリハビリシューズに明確な違いはなく、介護用靴の中でもリハビリの際に使う安全で動きやすい靴のことをリハビリシューズと呼んでいます。リハビリシューズには、リハビリを必要としている方が簡単に履くことができ、安全に歩けるようにサポートする機能が備わっています。
介護用靴の特徴
【介護用靴の特徴1】脱ぎ履きがしやすく、足を固定できる

脱ぎ履きなどがしやすく、足が固定できるのが特徴 です。 高齢になると、腰を曲げるのがつらい、視力の低下で足先が見えにくい、手先の動きが鈍くなって思うように動かせないという方でも、脱ぎ履きがしやすいように、履き口が広く自由に曲げやすい柔らかな素材でできています。かかと部分に輪が付いていて、引っ張るだけで簡単に履けるタイプもあります。足の固定は、ヒモではなくマジックテープで調整するタイプが多いです。 着脱が楽なのはもちろんですが、足の形状に合わせて簡単に固定 することができます。靴がゆるすぎると、靴の中で足が滑って転倒につながる恐れがあるため、マジックテープで簡単に固定できるのは、安全に歩くためにも安心な機能です。
【介護用靴の特徴2】左右で足のサイズが違う、片足だけでも購入できる
介護用靴は、 左右で違うサイズの注文や、片足だけでの購入 もできます。左右の足のサイズが違うと自覚している方や、病気などで片足だけむくむことが多い方、装具を着用した状態で靴を履く必要がある人など、 左右同じサイズの靴を履くことが難しい場合にとても便利 です。
介護用靴の種類
(1)リハビリシューズ

リハビリシューズは介護用靴と明確な違いはありません。ケガや病気などでリハビリが必要になったときに履く靴をリハビリシューズと呼びます。一般的な靴に比べて脱ぎ履きがしやすく、 伸縮性もあるので圧迫感を感じずに快適 に履くことができます。
(2)介護用靴
介護用靴には、高齢者が簡単に履け、 少しでも安全に歩くことができるように工夫されたデザインや機能 が備わっています。高齢になると足首の柔軟性が衰え、歩いているときにつま先が上がりにくくなるためつまずきやすくなります。このような 歩行中のつまずきを防止 するために、介護靴はつま先が少し上がっているデザインが多いです。つま先だけでなく、かかと部分が少し上がったデザインもあり、歩くときのけり出しや着地がしやすいような構造で、転倒防止にもつながるようになっています。
(3)介護用靴(半身麻痺や装具着用している方用)
半身麻痺の方、装具を着用している方用の介護用靴は、 足の甲の部分が開く、マジックテープなどで足の甲の高さに合わせて調節ができる など、 靴を履くときの負担が少しでも軽く なるように、さまざまな工夫がされています 。外反母趾やむくみによる圧迫感も考慮もされ、足先部分にゆとりがあるものや、伸縮性の高い素材が使用されているものが多いです。
介護用靴の選び方
①身体や症状に合う靴を選ぶ

介護用靴を履く人の身体状況に合ったものを選びましょう。 むくみや腫れがひどいときは、足幅のサイズ調整が簡単なマジックテープで固定できるタイプ がよいでしょう。リウマチや外反母趾などで 足先に痛みがある場合は、足先が柔らかい素材のものを選ぶ ことで、靴を履いて歩くときの痛みの軽減になります。足先に循環障害がある場合は、足先の感覚がわかりにくいことが多く、気づかないうちに足先を強く打っているケースも少なくありません。ケガ防止のためにも、足先がしっかりと覆われているタイプの靴を選びましょう。
②室内用と屋外用の靴の違いで選ぶ
介護用靴には、室内用と屋外用があります。室内用の多くは、素材が柔らかくて軽いものです。靴底に滑りにくい加工がされ、スリッパやソックス1枚で歩くよりも安心で、転倒防止にもつながります。屋外用は、撥水加工がされているタイプが多く、雨の日の外出も安心です。 室内用と屋外用では素材や構造が異なる ため、どこで履く予定なのかを考えて選びましょう。
③介護用靴のサイズだけでなく幅や高さにも注意
介護用靴を選ぶときは、足のサイズだけでなく、 幅や甲の高さなどが足に合っているかどうかも重要 です。 足のサイズでいえば、つま先に1cm程度ゆとりがあるものを選ぶとよいでしょう。足の幅は、親指と小指が靴に圧迫されることなく、側面にそっと触れる程度が最適です。足先にゆとりがないと、窮屈に感じ痛みが出るなどの恐れがあるため、中で足の指が広がるくらいを目安にして選びましょう。 足の変形やむくみがある方、装具を着用している方には、幅が広めのタイプがおすすめです。マジックテープで固定するタイプであれば、幅や甲の高さも調整しやすいので便利です。インソールが取り外せるものもあり、装具を着用している側のインソールを取り外し、身体のバランスをとりやすい高さに調整するという方法もあります。 サイズが合っていないと、指を痛める、靴の中で足が滑り転倒のリスク になります。しっかりと足に合った履き心地のよいものを選びましょう。 【靴のサイズの測り方】 足の大きさは、その日の身体状況や時間帯などによって変わることがあります。むくみが出やすい場合は、最もむくんでいる時間帯に足のサイズを測ってみることをおすすめします。また、多くの人が左右で異なる数値が出るため、必ず両足を測りましょう。
④ 装具使用の場合は、開口部が広い介護用靴を選ぶ
装具を着用していると、装具の大きさで靴が履きにくいことがあります。靴の甲部分が大きく開くタイプなど、 開口部が広い介護用靴を選びましょう 。 安全に歩くために、足を靴に入れたら、マジックテープなどでしっかり固定して足にフィットさせるようにしましょう。
⑤インターネットで買う場合も、一度試し履きしてからの購入がおすすめ
インターネットでも、介護用靴の購入ができます。ご自身のサイズが明確に分かっている、同じ物をリピートして購入するときなどにはとても便利です。しかし、介護用靴は、高齢になるにつれて感じやすい歩行に対しての不安解消や、病気やケガなどによる歩行時の身体への負担軽減をサポートすることを目的とした靴のため、はじめてご購入されるときなどは、 試し履きをしてからの購入をおすすめ します。フランスベッドが運営する介護ショップ 「リハテックショップ」では介護用靴の試し履きをすることができます
介護する側に適した靴

【1.デイサービスなどの職場で履く場合】
デイサービスなど靴を履く、脱ぐが多い職場では、紐のない靴がよいでしょう。紐があると履くのに時間がかかるため、送迎や靴の着脱介助などを行うときにすぐに適切な介助ができません。 さっと脱ぎ履きができる紐なしの靴を選びましょう 。
【2.介護施設などの職場で履く場合】
移乗介助などの身体介護が多い現場では、 フ ィット感があって足を保護できるジッパータイプの靴がよい でしょう。車椅子やベッドへの移乗などを安全に行うために、介護者の足を保護しながらしっかり踏ん張れる靴を選びましょう。 サンダルや紐靴は、ケガや転倒のリスクがある ため避けましょう。
【3.訪問介護で履く場合】
訪問介護では、訪問先で靴下に汚れが付いてしまうことあります。次の訪問先にそのまま行くことのないように、あらかじめ了承を得てビニールのスリッパなどを履くようにしましょう 。 ビニールのスリッパであれば、汚れが付いても簡単に拭き取り、水洗いも可能 ですのでおすすめです。
【4.介護を行うすべての人向け】
介護を行うときは、介護する方、される方、両方の安全を考える必要があります。介護する方は、足先が出ている靴、高いヒールの靴など機能性に優れていない靴を履いていると、介護中のケガや事故にもつながります。 安全に介護を行えるように足先がしっかりカバーされ、フィット感のある動きやすい靴 を選びましょう。介護する側の靴として、通気性がよく蒸れにくい靴、かかと部分が低い靴など、介護する上で必要な機能が備わった靴がたくさんあります。フランスベッドのECショップ「ホームケア全科オンライン」でも購入することができますので探してみてはいかがでしょうか。 ▶ 介護する方用の靴はこちら
まとめ
介護用靴は、 高齢になるにつれて感じやすい歩行に対しての不安解消や、病気やケガなどによる歩行時の身体への負担軽減をサポート します。 加齢や急な病気・ケガによってこれまでのように軽快に歩くことが難しくなった方でも、自分の足に合った履きやすい靴があれば、大きな負担を感じずに安心して歩くことができます。最近は、おしゃれなデザインの介護用靴もあります。靴を選ぶ楽しみや、お気に入りの靴が見つかれば、介護用靴を履いておでかけするという喜びにもつながります。介護用靴は、介護する側の方にとっても、介護の負担軽減や安全を守る大切なものです。 フランスベッドのリハテックショップでは試し履きできる ので、自分にあった介護用靴を選ぶことができます。もちろんフランスベッドのECショップ「ホームケア全科オンライン」でも、介護用靴を取り扱っています。たくさんある種類の中から、足に合う快適な介護用靴を見つけてみましょう。 ▶ 高齢者のための介護用靴の一覧はこちら
片麻痺の【背屈制限】には靴の踵に補高を入れよう
片麻痺の患者さんの歩き方を良くしたいんですが、良い方法はないですか? 患者さんによるけど、後ろ歩き訓練が一つの方法としておすすめですよ 後ろ歩きですか? 普段あまりしない治療です 後ろ歩き訓練はバラン.
脳卒中のリハビリの中止基準は?
脳卒中のリハビリって発症して早くに始めた方がいいんでしょ? そうですね。脳卒中は早期にリハビリを始めた方が良いと言われています。 脳卒中ガイドラインの2021でも「十分なリスク管理のもとに,早期座位・立位,装.
寝返り訓練で片麻痺の回復を促す方法
近年、片麻痺患者の治療では、早期に歩行を復帰させることがトレンドとなっています 科学的な根拠も揃っており、ガイドラインでも長下肢装具の利用が推奨されています そんな背景の中、脳出血・脳梗塞後の片麻痺患者に対して寝返り訓練が行わ.
脳卒中片麻痺の体幹崩れに対するアプローチ方法
脳卒中片麻痺のリハビリでは手足の麻痺に注目しがちになります しかし脳の中には手足以外にも体幹やバランスを支配する働きがあります 脳出血や脳梗塞により体幹を支配している部位も障害され体幹の機能が落ちることがよくあります そ.
【文献紹介】BBS(FBS)の検査で歩行自立度以外に「予後予測」も検証できる
BBSって定期的に検査をして点数を出すけど、点数を予測したりできないかなぁ BBSは取り入れている施設・病院も多い分、文献も多いですよね 文献ではよくカットオフ値の検討されますが、今回は予後予測の活用方法が記載されて.
脳卒中片麻痺患者の予後予測の方法
はじめに 脳卒中の患者さんの症状は多種多様に分かれて予後予測は大変ですよね 特にもともとの身体の使い方、歩き方がわからない状況にも関わらず発症された患者さんの予後予測は困難極まりないです 今回はそんな困難な予後予測の話で.







Comments